エヌ・デーソフトウェアとbrightvieは、両社の主力商品である介護業務支援ソフトウェア「ほのぼのNEXT」と、センサー情報一元管理システム「ケアデータコネクト」の連携を開始する。 今回の連携により、ケアデータコネクトに接続された複数の見守りセンサーなどから取得したバイタルデータや状態変化などの情報を、ほのぼのNEXTの介護記録システムに自動で取り込むことが可能になる。...
新着情報
介護技術活用の秘訣をネットで提供 善光総研🆕
善光総合研究所は介護領域のデジタル中核人材の育成事業の一環として、介護テクノロジー活用の習得と実践のノウハウをオンラインで提供するe-learningプラットフォーム「SCOP learning(スコップ ラーニング)」のβ版(テスト版)を公開した。 現場のDXを成功させるには個人のスキルアップだけでなく、組織全体での知識の標準化とAI・IoT・ロボットといった最新テクノロジーを使いこなすことが不可欠であることから開発した。...
「運動による老化時計の制御」の共同研究を実施🆕
日本郵政と東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター、大塚製薬は、「運動による老化時計の制御」に関する共同研究の契約を締結した。 「DNAメチル化老化時計(老化時計)」を活用し、1人ひとりの「生物学的老化度」を科学的に可視化する。 血液からDNAを抽出し、加齢に伴うメチル化パターンを解析することで、被験者個々の生物学的老化度を測定する。 具体的には、運動習慣のない中年層(約15人)を対象とし、3カ月間の中強度有酸素運動や高強度インターバルトレーニングを相対的な運動強度で実施する。...
転倒骨折予防「ころやわ」のより薄く軽い新製品🆕
Magic Shields(静岡県浜松市)は転倒時の骨折リスクを軽減するマット製品「ころやわ」シリーズの最新作「ころやわマットⅢ(スリー)」の販売を開始した。 新製品は衝撃吸収レベルを担保しつつ、従来製品に比べ厚さを約25%、重さを約18%それぞれ軽減した。 新たに4辺スロープを採用することで、課題だった側面からの汚れ侵入を防止するとともに、薄くなったことにより車いす利用での快適さも向上した。これまで清掃性や車いす移動が課題との声が寄せられていたが、そうした意見に対応することができた。...
2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」
第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。...
テーマ特集/対談・インタビュー

早期診断・早期対応へ 年間100件以上の認知症初期集中支援を実施 〔東京都世田谷区〕🆕
軽度認知障害(MCI)から認知症への移行や認知症の進行を遅らせるには、認知症の疑いのある人、あるいは認知症の人に、早い段階で支援を行うことが重要だ。その取り組みを行うのが全国の自治体に設置されている「認知症初期集中支援チーム」である。東京23区内の年間支援数が自治体によってかなり差がある中、世田谷区では年間100件以上の支援を実施し、そうした人たちの早期診断・早期対応につなげている。
■区内28カ所のセンターに支援の窓口
世田谷区の人口は今年4月1日現在約92万6000人で、65歳以上人口は約19万人。ただ、高齢化率は20.57%で全国平均の29.0%に比べれば低い。都心に近く、流出入率の高い20~30代の単身世帯が多いためだ。介護保険の要支援・要介護者数は4万2808人で、そのうち認知症高齢者数は2万5781人である。
高齢化率は低いものの、いくつかの県を上回る人口の多さと、東京・多摩地域屈指の商業都市である立川市の全人口に匹敵する高齢者数に対応するため、世田谷区では区内を5つの地域に分けて総合支所を設け、さらに各地域を分割した28地区すべてに地区行政の窓口である「まちづくりセンター」を設置している。
同センターの建物には「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」と社会福祉協議会の地区事務局も入っており、3者が連携して区民の困りごとなどに対応してきた。2022年度からは、この3者に児童館が加わり「毎月開催する4者連携会議で地区の課題を把握・共有し、地域包括ケア地区展開として地域づくりを行っている」(世田谷区高齢福祉部介護予防・地域支援課課長の横尾拓哉さん)。
この連携は認知症初期集中支援チームの活動にも貢献している。同課係長の北畠たまみさんによると「例えば、まちづくりセンターのミニコミ誌作成の委員だった人が日時や会場を頻繁に間違えるようになったとか、社協のサロンに定期的に参加していた人が会場までたどり着けなくなったとか、帰り道で迷うようになった」などまちづくりセンターや社会福祉協議会の活動で気になった情報をあんしんすこやかセンターに伝えることで、初期集中支援の対象者の発掘につながる」からだ。
■認知症初期集中支援事業
認知症初期集中支援事業は国の「認知症施策5カ年計画(オレンジプラン、2013~17年度)」で打ち出され、制度化に向け13年度から全国の14自治体でモデル事業を開始した。世田谷区は東京都で唯一の自治体として参画し、モデル事業の段階から国と連携して取り組んできた。
同事業では、在宅で生活している概ね40歳以上の認知症の人(疑いを含む)と家族を対象に、認知症初期集中支援チームが原則6カ月間、定期的に家庭を訪問する。
この間に、認知症に関する正しい情報を提供したり、認知症の進行や介護に関する心理的負担の軽減を図ったり、適切な医療や介護サービスにつなげたりすることで…
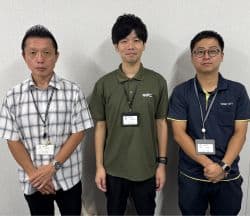
誰もが活躍できる地域づくりへ 国に先駆け認知症施策推進基本計画を策定〔和歌山県御坊市〕🆕
2019年に「認知症の人とともに築く総活躍のまち条例」を制定した和歌山県御坊市は、国の認知症施策推進基本計画に先駆け、21年4月に市の第1期認知症施策推進基本計画を策定した。同市では「総活躍」というキーワードのもと、認知症の人も含め誰もが活躍できる地域づくりを進めている。
■認知症条例から基本計画へ
市民の高齢化が進み、高齢者の7人に1人以上が認知症という状況を踏まえ、御坊市ではそれまでの認知症施策を総合的な取り組みに再構築するため、誰もが活躍できるまちづくりを目指す「ごぼう総活躍のまちづくりプロジェクト」を16年に立ちあげた。
このプロジェクトを進める中で、認知症の人が支援されるだけでなく、主体的により良く暮らしていくためには、市の責務と使命、理念を示した条例をつくるべきではないかとの声が関係者の間から出てきた。
それを受け、18年に認知症本人とその家族、認知症サポート医、介護関係者、市の職員ら13人が参加して「条例作成ワーキングチーム」を発足。4回の会議を重ね、翌年、条例を制定した。
条例は9条から成り、第3条で基本理念、第4条で市の責務を掲げ、第5条から第8条で認知症の人、市民、事業者、関係機関の役割を明記している。
基本理念では「認知症になっても自分らしい暮らしができること、いつまでも新しいことに挑戦できること、認知症の有無にかかわらず、すべての市民が活躍できること」を掲げている。
この理念を実現するために策定したのが認知症施策推進基本計画である。「国に計画を策定する動きがあり、いずれは市町村に策定が義務付けられることが想定されていたこと、それに条例を作った勢いもあったので、国に先立って作ってしまうことになった」と同市健康長寿課主任の丸山雅史さんは背景を説明する。
また、21年度は10年間の第5次御坊市総合計画と第8期介護保険事業計画の初年度であったことから、これらの計画とシームレスに連携しながら総活躍のまちづくりを進めようと考えたことも、この年に基本計画を策定した理由である。
ちなみに、24年度からスタートした第9期介護保険事業計画に合わせて第2期認知症施策推進基本計画を策定しており、それが現在の計画となっている。
■御坊市認知症施策推進基本計画
同計画では7つの指針を定め、指針1で「認知症・認知症の人への先入観の払拭」を掲げている。先入観が払拭されれば残り6つの指針で提示している取り組みが進展し、逆に他の指針の取り組みが進展すれば先入観が払拭されるとの考えからだ。
この「先入観の払拭」は、認知症基本法の国・地方公共団体の責務で「国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め…

「家族の権利宣言」発表 認知症本人と同じように家族への支援求める🆕
インタビュー 川井元晴さん(認知症の人と家族の会共同代表理事・山口県支部代表世話人、脳神経筋センターよしみず病院副院長)
45周年を迎えた「認知症の人と家族の会」は、6月の総会で「認知症の人とともにある家族の権利宣言」を発表し、認知症本の人への支援と同様に、家族への支援の必要性を訴えた。認知症の人と家族が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けていくために大切なことは何か。共同代表理事の1人である川井元晴さんに聞いた。
■業務量増加への対応で代表理事を2人体制に
――福井県支部世話人の和田誠さんとともに共同代表理事という形になったのは。
当会が設立されてから4代目の代表理事となる今回、定款を変え初めて2人体制になりました。役員についても、会の発足当初から活動に参加していた会員や理事から、若い世代へバトンを受け渡すような形で改選しています。
その理由として、ここ数年、認知症に関する状況が大きく変わってきていることがあります。アルツハイマー病の治療薬が上市されて使えるようになったことや、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が策定され、自治体が認知症施策推進基本計画を立てるようになったことなど、医療的にも社会的にもかなり様変わりしています。
認知症本人と家族についての社会的ニーズがとても多くなっている上、会への問い合わせや共同研究などが増えている中で、1人の代表理事だけでは対応が難しいことから、共同代表理事という体制となりました。
――今回の総会では、家族の権利宣言の発表もありました。趣旨は。
認知症基本法には「認知症の人と家族等」と、主語に家族も入っていますが、認知症本人の発信がとても大きなウエイトを占めていて、どうしても本人視点に重きが置かれます。このため、家族が置いていかれるような不安や危機感を持っている会員がいることから、家族も大事なのだということを宣言しました。
宣言自体は抽象的ですけれども、その解説版を作成中で、宣言と解説版をセットにして、各都道府県支部の世話人や自治体、地域の人たちと、権利宣言をどう活用していったらいいのかを考えていくことにしています。
――認知症施策推進基本計画については。
各自治体が基本計画を策定するにあたり、本人と家族が参画することになったのはとても重要です。
ただ、私は山口県支部の代表世話人も兼務しており、県の基本計画の策定会議に参加していますが、行政の書類が独特な様式と内容で書かれているため、策定案を議論するのに、本人と家族はついていくのが精一杯のような状況で、行政の会議に本人と家族が参画する上での課題と改善点が浮き彫りになった感じがします。
――本人の意見をどう聞いたらいいか、計画を策定する人たちは悩んでいるようですが。
意見が聞けるのは診断当初の人や軽度認知障害の人など、症状が比較的軽めの人が想定され、その中でもしっかりと自分の考えを自分の言葉で発信できる人ということになりますと、意見を言える人は限られるでしょう。
基本法の対象は認知症の人と家族全体なので…

訪問主体も小多機・看多機拠点に地域と交流 自社になければ他施設活用する工夫を 板井佑介・ケアメイト代表取締役 下🆕
■看多機と小多機の区別は意味がない
――看多機でもいいのですか。
看多機と小多機を区別することには、あまり意味がないと思います。小多機は認知症の人、看多機は医療依存度の高い人、みたいなくくり方をすると、そういう人たちだけが集まって同質化してしまう。そうすると、化学反応が起きない。
状態の異なる人がいるから、化学反応が起こる。例えば元気な認知症の人が、寝たきりになっている人に一生懸命声をかけて励ましたりするわけです。
――駄菓子屋もありますね。そうした子どもたちも高齢者と交流するのですか。
フロアに上がってきたり、慣れた子はここを待ち合わせ場所にしたりしています。高齢者も本人が望めば接客したり、お金の計算をしたりしています。全然勘定が合いませんけれど。一緒に百人一首などをやっていることもあります。
介護とか看護とか保育とか、そこの縦割りを壊すというか、地域包括ケアとか地域共生社会とか言われるものの具体的なひとつの姿を目指していると言えます。
ただ、それにはスタッフのコーディネート・スキルがすごく大事で、さすがに何もしないでいきなり高齢者と子どもたちが交流することはありません。その点、自分からそういう状況を作ることが出来る職員がまだまだ少ないのが課題です。
■地域共生に対する感性を持つことが大事
――訪問だけで地域の多様な人たちと交流を図るのは難しいですか。
難しいというか、それだけでは面白くないということです。集まる場があることが大切ですし、地域共生に対する感性を、訪問であってもケアマネジャーであっても、持てるかどうかが大事だと思います。自分のところに拠点がなくても、世の中にいくらでもありますから。
例えば看多機で、先日、香川県の事業所と一緒にリモートでうどん作りをやりました。看多機のご利用者さまとご家族が参加しましたが、別にその人たちしか出入りしてはいけないとは言っていません。
弊社のケアマネジャーが担当している高齢者で、普段はここを使ってないけれど、外出支援の形で来るようなプランを立ててうどん作りに参加すれば…

訪問主体も小多機・看多機拠点に地域と交流 自社になければ他施設活用する工夫を 板井佑介・ケアメイト代表取締役 上🆕
訪問介護・居宅介護支援を中心に事業を行ってきたケアメイト(東京都品川区)は、小多機・看多機・保育の各事業を始めたことで、高齢者と子どもたちとの触れ合いや地域住民との密接な交流が図れるようになった。板井佑介代表に地域とのかかわりを中心に聞いた。
■家政婦紹介所を基に地域で70年の歴史
――ケアメイトの創立は。
70年ほど前に祖母が家政婦紹介所を開設したのが始まりです。法改正で付添婦が廃止になって介護保険ができることになり、当時の家政婦紹介所はこぞって介護事業を始め、当社も父がケアメイトを立ち上げました。ちなみに、家政婦紹介所は「城南ケアサービス」と名称を変え、母が事業を継続しています。
私は大学を出て生命保険会社に入社し、11年ほど勤めた後、父が亡くなったため、2011年にケアメイトを継ぐことになりました。現場を知らないまま、いきなり経営者として入ったので大変でした。
――現在の体制は。
本部のほか、品川区を中心に8つの営業所があります。「在宅ケア&多世代共生拠点『けめともの家・西大井』」と称している品川営業所では、訪問看護・居宅介護支援・訪問看護・看多機・地域保育の各サービスを提供しています。
そのほか、大田営業所・目黒営業所・桜新町営業所で訪問介護と居宅介護、荏原営業所と港営業所では訪問介護、品川八潮営業所では小多機、品川二葉営業所では食支援・配食サービスを行っています。従業員数は常勤がパートも含めて70人ぐらい、登録のヘルパーが130~140人ぐらいいます。
――高齢者と障害者の訪問介護を行っているメリットは。例えば、両方やることでヘルパーの待機時間を減らすことができるとか。
おそらく介護保険制度ができる前から両方やっていますが、結局、オペレーションの問題なので、高齢者だけでも障害者だけでも、マネジメントさえきっちりできていればやっていけると思います。
むしろ、障害の状態はいろいろあり、移動支援などは長時間、付き添う必要がある場合もあります。それが毎週決まった曜日にあるわけではないので、時間だけでの相互補完的意味は、私の感覚ではあまりありません。
■制度改定に振り回されない
――訪問介護の倒産件数が過去最多を記録する中で、事業がうまくいっているのは。
介護報酬減額の影響は大きく、この辺りでも最近、廃業したところがあります。それでも弊社が曲がりなりに続けていられるのは、簡単に言えば、訪問に行く人がいるからです。
介護保険制度が始まる時点で家政婦がたくさんいて、その人たちにヘルパーの資格を取ってもらったので、いきなり100人規模のヘルパーがいる状態でスタートできました。しかも当初、競争がない中で地盤が築けたのが大きいと思います。
また、介護の仕事は常に制度に揺り動かされますが、それにあまり右往左往しないこともそこそこやれている要因かもしれません。例えば今だと「介護保険だけでは厳しいから、保険外サービスを」みたいな動きがありますが…

高齢者の住まいの過去・現在・これから 下🆕
■肝は介護保険事業計画が達成されないこと
田村 介護保険制度では、保険者(市区町村)は3年ごとに介護保険事業計画を策定します。事業計画には、各サービスをどれだけ整備するか、という計画値(整備目標値)が盛り込まれます。計画値は、ニーズ調査に基づく見込み量から算出されます。
当社では施設・居住系サービスについて、第3期(2006~08年度)事業計画から現在の第9期(2024~26年度)まで、計画値と、実際の整備量(都道府県がまとめる)を追いかけています。計画値と実績値をウォッチしているのです。
髙橋 とても貴重なリサーチです。
田村 なんと、第3期以降ずっと、計画値のほぼ7掛けぐらいしか整備できていないんです。達成率が最も高かったのは第7期(2018~20年度)の87.9%で、最低は第8期(2021~23年度)の66.3%でした。計画値そのものも、期を重ねるごとに縮んでいます。
髙橋 高齢者が増え介護保険サービス利用者の数も増えているのに。
田村 ここが一番の肝だと私は思っています。介護保険事業計画は介護保険事業の屋台骨といえます。ところが、ニーズに基づいて計画したにもかかわらず、その7割程度しか整備できない。それはすなわち…

高齢者の住まいの過去・現在・これから 中🆕
■供給先行で普及したサ高住
髙橋 サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)が登場したのは2011(平成23)年ですね。当時の厚労省老健局長は、サ高住のコンセプトを“厚生年金受給者が入居できる質の高い高齢者住宅”と説明していました。
ところが、今やサ高住は住宅でなく施設のように扱われ、囲い込みの問題も出てきています。サ高住をどう評価されますか。
田村 サ高住が登場したのは「介護保険安定期」です。サ高住の前身は高専賃で、さらにその前は高優賃でした。これらをベースに2011年、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)を改正し、サ高住が誕生しました。
そもそも高専賃のニーズはそれほど高くなくて、供給量も年間1万戸程度だったんです。ところがサ高住については、1室当たり100万程度という破格の補助金を出しました。この補助金は、土地持ちや、工務店、設計事務所、ハウスメーカーといった人には魅力的で、みんなそこに飛びついて、年間4万~5万戸と、一気に供給が進みました。
つまりサ高住に住みたいというニーズがあったから供給が進んだわけじゃなくて、先に供給サイドに火がついた。造れば目的が達成されるわけですから、造ったあと、入居者の生活支援をどうするか、その発想がないまま…

高齢者の住まいの過去・現在・これから 上🆕
■高齢者住宅の誕生から現在
髙橋 本日は田村明孝さんと、有料老人ホームなど高齢者の住まいについて語り合います。田村さんといえば、高齢者住宅の業界ウォッチャーの第一人者として知られます。まず、高齢者住宅の歴史を振り返りましょう。
田村 私と業界との付き合いは50年ほどになりました。高齢者住宅・施設の変遷を追うと、以下のように、いくつかの時期に分かれます。
最初は「高齢者住宅黎明期」。1970(昭和45)年、有料老人ホームの先駆けとなるものが出始めました。有料老人ホームはその少し前、1963(昭和38)年に制定された老人福祉法の29条に「届け出制」と規定されたことをきっかけに登場しました。
髙橋 老人福祉法では、行政が関与する措置施設の「養護老人ホーム」、今で言う要介護老人を入居させる「特別養護老人ホーム」、健康老人向けの「軽費老人ホーム」が施設体系として規定されました。
養護老人ホームは生活保護法に規定された「養老院」を継承した、低所得階層向けのいわゆる救貧施設でした。特別養護老人ホームの入居には所得制限があり…
コラム

第65回 デンマークの「生活支援法」と日本🆕
ワンストップの窓口 11月、国立市が実施する「シニアカレッジ」で講師を務めた。市民を対象に、高齢期の健康・福祉や国立市について学ぶもので、今年で10年目となる。 テーマは「保健・医療・福祉サービスの日欧比較」。私にとっても、久しぶりに日本の介護保険と外国の制度をじっくり考える機会となった。そこで、高齢者ケアの先進国として知られるデンマークの「生活支援法」を題材にした。...

第64回 「100歳まで生きたいですか」を考えた🆕
「いいえ」が61% 朝日新聞土曜版「be」に、毎回、読者モニターへのアンケートが掲載されている。9月27日付は「100歳まで生きたいですか」という設問であった。 これに対して、「はい」は39%、「いいえ」が61%であった(回答者数は2476人)。「世論調査のような統計的意味はありません」という調査だが、この比率は、日本人の心情をある程度率直に反映しているのだろう。...

第63回 安楽死の前に過剰緩和を議論すべきだ🆕
安楽死が合法の国が増えている 安楽死が合法である国・地域はオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、ポルトガル、カナダ、コロンビア、エクアドル、ニュージーランド、オーストラリア・ヴィクトリア州である。スイス、ドイツ、イタリアとアメリカのいくつかの州では医師による自殺幇助が合法だ。 この1年ほどの間に、イギリス下院とフランス下院で安楽死法案が相次いで可決された。安楽死の合法化はヨーロッパを中心に広がっている。...

第25回 医療費削減の切り札? 医療用医薬品のOTC移行🆕
国民医療費の削減によって社会保険料を下げるという提言が出てきています。その中にOTC類似薬の保険適用除外を進める案があります。自民党、公明党、日本維新の会の3党は2025年6月11日、OTC類似薬の保険給付のあり方の見直しなど社会保障改革に関する政策について合意しました。 OTC類似薬とは、OTC医薬品とほぼ同じ成分や効果を持つ医療用医薬品で、医師の処方箋がなければ入手できません。現在、こうしたOTC類似薬は医療保険の対象ですが、対象から外していこうという方向性が打ち出されたことになります。 ■OTC薬とOTC類似薬 OTC薬とO...

第62回 101歳・認知症女性のひとり暮らし
100歳以上高齢者の総数は今年9月15日現在、9万9763人である(住民基本台帳に基づく)。前年から4644人増え、来年は確実に10万人を超えるだろう。 ■ヘルパーとコミュニケーション 新田クリニックが訪問診療を提供しているT子さんは101歳、自宅で一人暮らしをしている。5月ごろまでは家の中を歩くことができたが、脱水症を起こしたことがきっかけで起き上がれなくなり、今はほぼ一日中、ベッド上で過ごしている。 認知機能は年相応に低下している。短期記憶障害が著明で私の顔も覚えていないが、重度の認知症とはいえない。持病は…、T子さんが検査を...

第19回 介護人材不足の実相から対策を考える
■実は増え続けてきた 人材不足は、介護業界における慢性疾患ともいうべき癒えることのない苦しみです。今回は、これに対処するために大きな変革が急務であり、その変革とは何か、お伝えしたいと思います。 介護人材不足については、さまざまな事実誤認があります。「この10年、介護人材は減少を続けている」あるいは「介護人材はなんとか増えているものの、要介護者の増加には全く追いついていない」と感じている方は多いのではないでしょうか。 最近では訪問介護事業所の倒産件数が過去最高を記録したという報道もあり、「訪問介護サービスの供給量が減少している」とい...
現場ルポ/医療介護ビジネス新時代

簡単に送迎計画作成の「らくぴた送迎」提供 施設の枠を超えた福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」も展開〔ダイハツ工業〕🆕
ダイハツ工業は2018年から提供している送迎支援システム「らくぴた送迎」により、デイサービスの業務負担の約3割を占める送迎の効率化を進めている。さらに22年から提供を開始した福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」によって、地域全体での効率的な送迎システムの構築を目指している。
■利用者カードを車両の枠に移動して作成
らくぴた送迎を開発することになったのは、2015年4月に社内で福祉の専門チームを立ち上げ、同社の社員がダイハツディーラーと一緒に全国の介護施設へ福祉車両の訪問営業をする中で、デイサービスでは送迎計画の作成に苦労しているという声を数多く聞いたことがきっかけだ。
そこで聞いた現場の苦労の声を基にして、らくぴた送迎の開発を進め、システムと専用スマートフォンにより「送迎前」「送迎中」「送迎後」の各シーンで課題を解決するソリューションとして提供を開始した。
クラウドサービスなので、パソコンとインターネットが使える環境なら、ソフトをインストールする必要がなく送迎計画を作ることができる。申し込み後に1事業所あたり1ライセンスを発行する。利用料は1万5000円/月(税込み1万6500円/月)。
送迎中・送迎後のサービスを利用するには専用モバイル端末(スマートフォン)が必要で、3000円/台(同3300円/台)とモバイル端末保証料273円/台(同300円/台)でレンタルする。
送迎計画の作成では、まず準備として「利用者マスタ」「車両マスタ」「職員マスタ」「事業所マスタ」の各項目に必要情報を入力する。
利用者マスタには利用者の情報を入力するが、らくぴた送迎が連携している「ワイズマン」だけでなく、他の介護記録ソフトからもCSVデータを読み込むことで、すべての利用者の名前や住所、生年月日、電話番号、利用日などの基本データを一括して入力できる。
あとは車いすや歩行器のあるなし、家の道が狭い場合等の軽自動車専用、相性が合わない利用者、希望する移動時間、薬などの持ち物といった詳細情報を入力することで利用者マスタは完成する。家と利用者の写真等も入れられるので、初めて行く職員もスマホを使えば家や利用者を間違えることはない。
車両マスタには車の種類や乗れる人数、車いす搭載の可不可など、職員マスタには担当業務や運転可能な車両サイズなど、事業所マスタには事業所の情報を入力する。
計画策定画面にはカレンダー機能があり、日を選ぶとその日の車両と利用者のデータが画像の形で出てくる。作成者は、利用者の名前が表示されたホワイトボードのマグネットのような四角い枠をドラッグし…

公社初の「シニア住宅」を小金井市に建設供給 多世代交流へ「シェアリビング」も初めて設置 〔JKK東京〕🆕
JKK東京(東京都住宅供給公社)は、小金井市の「小金井本町住宅」の団地再生事業で、新築賃貸住宅「カーメスト武蔵小金井」内にJKK初となる「シニア住宅」を整備した。同住宅はバリアフリー設計とし、見守りサービスを付けて提供するサービスを限定することで、これまで供給してきたサ高住に比べ家賃負担の軽減を図った。また、住民が無料で使用できる「シェアリビング」を設けて世代交流を図るなど、高齢者向け住宅の新たな形を提示している。
■市の要望を受けシニア住宅を提案
小金井本町住宅は最寄り駅であるJR中央線武蔵小金井駅から歩いて約15分、同駅からのバスで約9分の中規模団地である。1960~61年に830戸が建設されたが、老朽化によって一部が建て替えられることになり、2020年からJKKと小金井市が団地のあり方について協議を開始した。
その中で、同市から示されたのが、同地区の高い高齢化率を反映した「高齢者が安心して暮らせるような福祉施設を整備する」という要望だった。
JKKではそれを受けて検討を行い、福祉施設だけでなく、「高齢者が低廉な負担で、住み慣れた地域で安心して住み続けられるような団地の建替事業」という構想の下、シニア住宅の建設を提案した。
さらに、手狭で交通アクセスが良好ではなかった「小金井にし地域包括支援センター」を移設する案も提示。協議の結果、これらの施設・住宅の建設が決まり「小金井本町あんしん住まいプロジェクト」として計画がスタートした。
第1弾として高齢者福祉施設「本町けやきの杜」が2023年8月にオープンした。第2弾として賃貸住宅「カーメスト武蔵小金井」内のシニア住宅40戸が竣工し、昨年12月から入居者の募集を開始。第3弾では一般住宅棟に併設して建設された地域包括支援センターが…

介護施設向けシフト自動作成サービス「miramos」発売 特許出願技術で作業時間を大幅に短縮〔コニカミノルタ〕🆕
コニカミノルタはこのほど、AIを搭載した介護施設向けシフト自動作成サービス「miramos(ミラモス)」を発売した。特許出願中の「夜勤・公休先行配置」により、少ない手直しで完成でき、シフト表作成にかかわる作業時間を大幅に短縮した。
■介護施設の要請でシフト作成ソフトを開発
以前は複合機のソフトウエア開発を行っていた、デジタルワークプレイス事業本部miramosプロダクトオーナーの森田光貴さんがこのソフトを開発することになったのは、介護関連の機器・システム開発を行っているQOLソリューションズ事業部からの相談がきっかけだった。
複合機は成熟した市場なので、新規事業を模索していたところ「介護報酬制度では加算の取得が必要不可欠だが、その要件が複雑なので介護施設が困っている。なんとかできないか」ともちかけられたのである。
シフト表から解析すれば、加算の要件を満たすかどうかをチェックできることがわかり、協力してくれることになった複数の介護施設からシフト表を提供してもらい、どのような加算が取れるかを判定してくれるソフトを開発した。
それを持って施設に行ったところ、既存のシフト作成ソフトは使い勝手が悪く、依然としてExcelや手書きで作成しているので、シフト表も作ってほしい、との要望が寄せられたためmiramosを開発することになった。
2023年4月に着手。最初は施設側から「完璧なものじゃなくても、ベースができるだけですごくありがたい」と言われたこともあり、9割ぐらいの完成度でシフトを作成するソフトを作った。
「これでいけるだろう」と最初は思っていたが、施設に持って行ったところ、使ってもらえなかった。実は残りの1割の部分が重要で、そこが既存のソフトが使われていない原因だったのである。中でも最大の問題が「夜勤」をずらすことだった。
■2段階でシフトを組むことで課題を解決
通常、夜勤は「夜勤明け」「公休」とセットになっており、夜勤をずらすと、3日分をずらさなければならない。
その3日先に「早番」「遅番」などが入っていると、それもずらすか、他の人に振り分ける必要がある。そうすると、玉突き状態で次々に修正しなければならず…

介護タクシーで高齢者が気軽に外出できる社会へ 予約アプリ「よぶぞー」を提供〔IT FORCE〕🆕
企業向けのシステム開発を行うIT FORCEが2023年3月から提供している、介護タクシー予約アプリ「よぶぞー」の登録者数が5000人を突破した。同社ではこのアプリの利用が広がることで、高齢者が気軽に外出できるようになることを目指している。
■開発のポイントは社会貢献とビジネスの両立
同社は06年に創業し、14年から米セールスフォースのコンサルティングパートナーとして、営業支援や顧客管理など、業務を効率化するシステム「セールスフォース」を国内企業に導入する支援を行っている。
業務の拡大を図るため、20年ごろから陰山光孝社長をはじめ経営陣が今後の方向性を検討したところ、蓄積したデジタルやITの技術を活用して社会に貢献していくことが、結果的に企業の発展につながるのではないかとの結論に達し、社会課題に挑戦していくことになった。
介護タクシーに着目したのは「そのころドライバー不足と、団塊の世代が後期高齢者になるという課題がメディアを賑わせており…

インナータイプのアシストスーツ「DARWING UT-Rise」発売 薄く涼しく着やすさを追求〔ダイヤ工業〕🆕
ダイヤ工業(岡山市)はインナータイプのアシストスーツ「DARWING UT-Rise(ダーウィン ユーティーライズ)」を発売した。現在、アシストスーツは服の上から装着するアウタータイプが主流だが、装着性の良いインナータイプを普及させることで、さまざまな現場で働く人にとって、アシストスーツがより身近なものになることを目指す。
■筋肉スーツからアシストスーツへ
ダイヤ工業は1963年の創業で、主に接骨院・鍼灸院・クリニックなどに向けて、日常用・スポーツ用サポーター・コルセットの開発・製造・販売を行っている。
同社がアシストスーツを手掛けるようになったのは、筋肉スーツを製品化したことがきっかけ。「首から指先までほぼすべての部位のサポーターを作っており、サポーターの集合体のようなものを作りたいと考え、全身筋肉スーツを開発することにした」と広報の藤原舞利子氏は説明する。
特徴は「二層構造で膝を持ち上げるパーツがあるので歩くのを補助したり、腰のサポートパーツが腰を支える機能を設けたこと」(藤原氏)。
高齢者がいつまでも元気に活躍するサポートがしたいと考え開発したものの、スポーツから作業現場での労働支援など、特にジャンルは特定しなかったが…
政策・審議会・統計
2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」
第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。...
制度見直しの議論続く 介護保険部会
第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。 「拡大すべきでない」論者の意見は、...
2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会
第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。 このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。...
訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く
東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。 人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。 25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...
2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会
第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。 今回、「持続可能性の確保」は ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準 ●補足給付に関する給付の在り方 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方 の3つの論点に絞って議論された。...
業界の動き
「ほのぼのNEXT」と「ケアデータコネクト」が連携🆕
エヌ・デーソフトウェアとbrightvieは、両社の主力商品である介護業務支援ソフトウェア「ほのぼのNEXT」と、センサー情報一元管理システム「ケアデータコネクト」の連携を開始する。 今回の連携により、ケアデータコネクトに接続された複数の見守りセンサーなどから取得したバイタルデータや状態変化などの情報を、ほのぼのNEXTの介護記録システムに自動で取り込むことが可能になる。...
介護技術活用の秘訣をネットで提供 善光総研🆕
善光総合研究所は介護領域のデジタル中核人材の育成事業の一環として、介護テクノロジー活用の習得と実践のノウハウをオンラインで提供するe-learningプラットフォーム「SCOP learning(スコップ ラーニング)」のβ版(テスト版)を公開した。 現場のDXを成功させるには個人のスキルアップだけでなく、組織全体での知識の標準化とAI・IoT・ロボットといった最新テクノロジーを使いこなすことが不可欠であることから開発した。...
「運動による老化時計の制御」の共同研究を実施🆕
日本郵政と東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター、大塚製薬は、「運動による老化時計の制御」に関する共同研究の契約を締結した。 「DNAメチル化老化時計(老化時計)」を活用し、1人ひとりの「生物学的老化度」を科学的に可視化する。 血液からDNAを抽出し、加齢に伴うメチル化パターンを解析することで、被験者個々の生物学的老化度を測定する。 具体的には、運動習慣のない中年層(約15人)を対象とし、3カ月間の中強度有酸素運動や高強度インターバルトレーニングを相対的な運動強度で実施する。...
転倒骨折予防「ころやわ」のより薄く軽い新製品🆕
Magic Shields(静岡県浜松市)は転倒時の骨折リスクを軽減するマット製品「ころやわ」シリーズの最新作「ころやわマットⅢ(スリー)」の販売を開始した。 新製品は衝撃吸収レベルを担保しつつ、従来製品に比べ厚さを約25%、重さを約18%それぞれ軽減した。 新たに4辺スロープを採用することで、課題だった側面からの汚れ侵入を防止するとともに、薄くなったことにより車いす利用での快適さも向上した。これまで清掃性や車いす移動が課題との声が寄せられていたが、そうした意見に対応することができた。...
製品事故リスク低減評価の新制度を受賞 マツ六
マツ六(大阪市天王寺区)の「遮断機式手すり」=写真=が、今年度からスタートした経済産業省主催の新制度「誤使用・不注意による製品事故リスクを低減した製品に対する表彰・表示制度(+あんしん)」を受賞した。これにより、「(プラス)あんしんマーク」を表示することができるようになった。 同製品は開口部の前や通路の横断など、手すりが途切れてしまう場所でも、開閉式にすることで行きたい場所まで手すりをつなげることを目指している。...
1週間無料でお試し購読ができます 詳しくはここをクリック
新着記事は1カ月無料で公開
有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題
*1年間は1万1000円(同)
〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料
【アーカイブ】テーマ特集/対談・インタビュー
コラム一覧
【アーカイブ】現場ルポ/医療介護ビジネス新時代
アクセスランキング(1月19-25日)
- 1位
