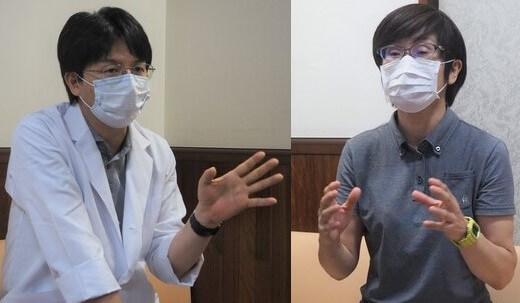国が後押しする介護ロボットのうち、最も普及が進んでいるのが見守り機器である。コニカミノルタの「HitomeQ ケアサポート」は見守るだけでなく、データを活用して介護業務を支援する。介護職の効率的な働き方を実現し、ケアの質の向上に貢献している。
■新ブランド「HitomeQ」立ち上げ
同社は昨年10月、新たなブランド「HitomeQ(ひとめく)」を立ち上げ、それまで展開してきた見守り機器事業を、介護施設の業務全般を支援する事業へと進化させた。この言葉には「一人ひとりを想い、考え、ひらめくという思いが込められている」とQOLソリューション事業部事業戦略部企画グループの斉藤朋之グループリーダーは話す。HitomeQにはケアサポートシステムのほか、同システムを使いこなすための「ケアディレクター」や「ケアルーペ」などのサービスやツールが設けられている。
ケアサポートシステムは行動分析センサーとケアコール(ナースコール)スイッチ、Wi-Fiのアクセスポイント、システム管理サーバーで構成される。各室の天井に取り付けるセンサーは……