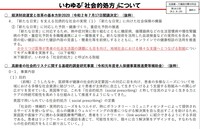■地域資源をマネジメントするための計画へ
行政の介護・高齢者部門では、現在、第8期介護保険事業計画(以下、事業計画)の策定がすすめられています。来春から3年間の介護保険給付及び地域支援事業の事業量を見定め、保険料を計算するための計画です。
介護サービスの量的見込に偏りがちだった事業計画でしたが、第6期(2015~2017年度)からは、専門職資源の質的なつながりを目指す「在宅医療・介護連携推進事業」や、地域の多様な資源の発掘・開発といった「生活支援体制整備事業(地域づくり)」の戦略も盛り込まれるようになり、別名として「地域包括ケア計画」とも呼ばれています。
介護保険が始まった20年前は、どの自治体も初めての計画策定に試行錯誤を繰り返したものですが、近年は、保険料推計の手法の確立などもあり……