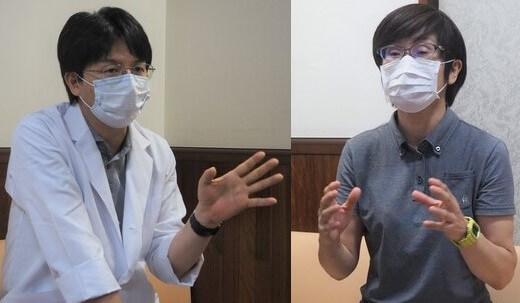このコーナーのタイトルは、「そろそろ社会保障のこと、まじめに考えたらどうだ。。。」である。連載の2回目には、「まじめに考える」ということはどういうことなのか? について書いてみようかと思う。
■なぜ人は年金に関して誤った信念を抱くのか
しばしば、次のような話をする。
日本ではもちろん、世界中で大ベストセラーとなっている『ファクトフルネス』の著者ハンス・ロスリングは公衆衛生を専門とする医師、そして、マイクロソフトのビル・ゲイツに「世界は良くなり続けている。たとえ、いつもはそんなふうに思えないとしても。…大局的な視点から世界の姿を我々に見せてくれる」と評さていた『21世紀の啓蒙』の著者スティーブン・ピンカーは言語能力の獲得過程を研究してきた言語学者・心理学者、それから、『ちょっと気になる社会保障』などの著者である私(笑)は経済学者――おそれながら、彼らにはある種の共通点がある。さて、それは何?
それは、彼らの論には認知とか本能という言葉が何度もでてくることである。
私は、2004年に行われた年金改革の大騒動の頃から、いいかげんな年金論を言う論者達に、それ間違えているよっと諭(さと)す、年金誤解を解く請負人、鬼退治をする桃太郎侍のような役回りにさせられていた。あれからもうすぐ20年近くなるのであるが……