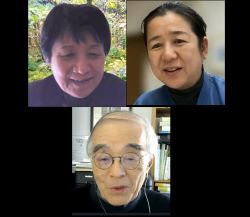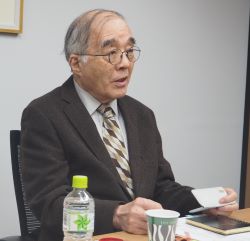髙橋 今回のゲストは、横浜市の社会福祉法人「訪問の家」の名里晴美理事長です。「訪問の家」は障害者向けの通所施設やグループホーム、地域活動ホーム、多機能型拠点などの事業と、高齢者向け事業、それに診療所も運営し、先駆的な実践を次々に展開してきたことで知られています。
「訪問の家」は、前身から数えると誕生から50年を過ぎました。創設者である日浦美智江前理事長は、重症心身障害児者の地域生活を先駆的に支援され、名里さんはその後継者です。本日は「訪問の家」の歩みを中心に、障害ある人とともに生きることについてお話しいただきたいと思います。
■スタートは「訪問学級」「母親学級」
名里 社会福祉法人「訪問の家」の発端は、1972年(昭和47年)にさかのぼります。この年、横浜市立中村小学校に訪問学級が開かれ、前理事長の日浦美智江がその母親グループの担当となりました。
これは重症心身障害児の学級で、当時の言葉でいう養護学校の学級版とでもいいましょうか。特殊学級というのは、障害が比較的軽い子どもが対象なので。
髙橋 障害が重い子どもへの教育は、かつては盲学校・聾学校・養護学校に分かれていて、養護学校には知的障害・肢体不自由・病弱の子が通っていました。障害の軽い子は小中学校では特殊学級に通っていました。
養護学校への就学が義務化されたのは1979年(昭和54年)ですから、中村小の訪問学級は義務化より7年も早かったわけですね。2007年度(平成19年度)より、盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校に、特殊学級は特別支援学級となって現在に至ります。
名里 市立小学校に訪問学級を設置し、重い障害のある子どもたちが通う、っていうことを、義務化に先んじて始めました。小学校の一室なので…